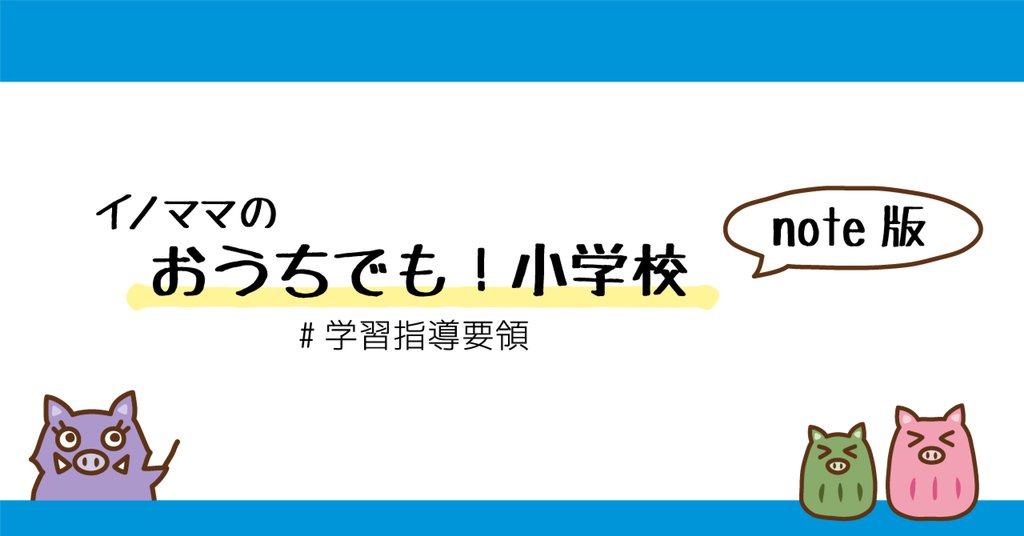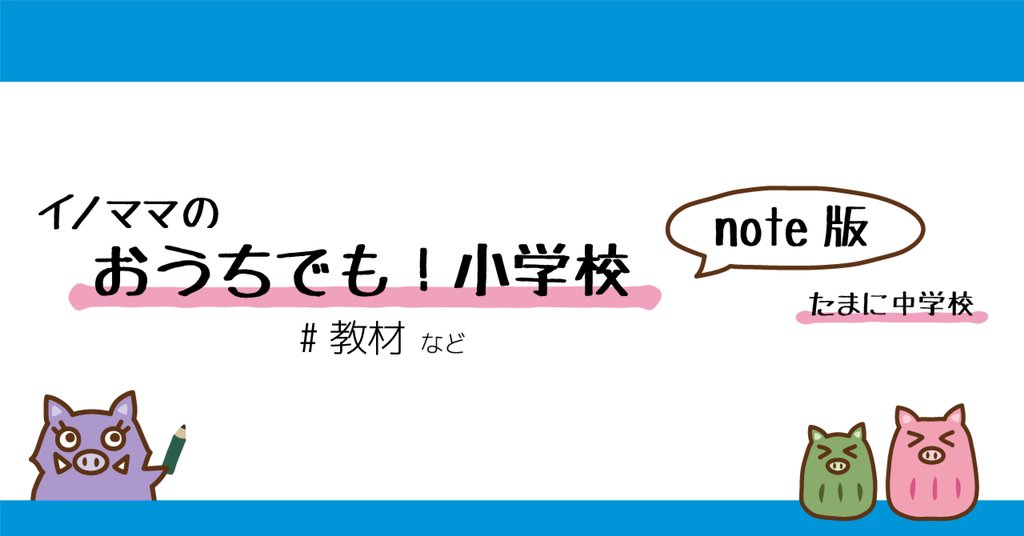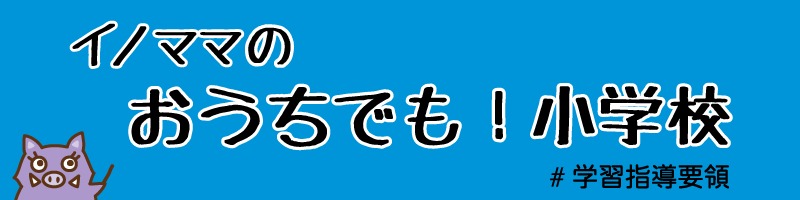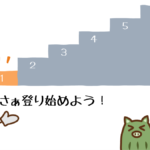こんにちわ、訪問ありがとうございます!
はじめに
前回の記事「小学校算数1年生の単元と項目」で内容一覧を、具体的には『 内容領域ごとの「単元名」「項目名」』をご紹介しました。

それだけでも十分かもしれませんが、学習指導要領 公式解説には、なるほど!と思う詳しい内容が沢山載っています。
家庭学習をサポートする上で、知っていて損はないと思います。よって今回から、公式解説を基にまとめた「項目の詳細説明」を、前回ご紹介した「項目名」に沿って 一覧にして ご紹介していきます。
一度にご紹介するとボリュームが多くなりすぎますので、領域ごとに記事を分けます。それでは今回は詳細1領域目、「小学校算数1年生【数と計算】の項目詳細」です、見ていきましょう!
【数と計算】領域について
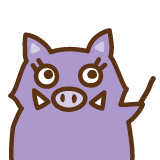
1年生の単元一覧
1年生で学習する【数と計算】領域の単元は、以下になります;
【数と計算】 – 単元一覧 :1年生
各単元の項目詳細
以下より、算数1年生の【数と計算】領域中の単元「数の構成と表し方」「整数の加法・減法」の各項目について、詳細を どんどん ご紹介していきます!
- 各単元ごとに「項目名」「項目詳細」が記載してあります
数の構成と表し方
- 様々なものの個数を比べる
- それぞれの個数を数えるだけではなく、おはじきなどと1対1の対応を付けることでも、個数の比較ができることを理解する
- 見えないもの(音の回数など)や 手元で操作できないもの(校庭の木など)も、おはじきなどと1対1に対応させれば、その個数で数を比べられることを知る
- 様々なものの個数や順番を、数えたり表したりする
- ものの個数を数える際、数えるものの集合を明確に捉える
- 数える対象に数詞を順に対応させて唱えると、最後の数がものの個数を表すことを理解する
- ものの順番を調べる場合は、対象に数を順に対応させていき、その対応する数がその順番を表すことを理解する
- 最後の順番を表す数は、個数を表す数と一致することを理解する
- 数としての0が用いられる場合を理解する;
- 「何もない」という意味の場合
(ゲームで得点がない場合や、実際の物の数が1ずつ減少していって最後はなくなる場合など) - 数の位の空位を表す場合
(70の一の位や 205の十の位 など) - 数直線での基準点 など
- 必要な場合に、0も他の数と同様に、数として見られるようにする
- 数の大小や順序を考える
- 数直線を用いて数の大小や順序や系列(=一列に並んだものの順番など) などを示すと、分かりやすく表せることを知る
- 必要に応じて、目盛りの単位が5や10などでまとめて示されている数直線や、途中から目盛りが始まる数直線も用いられることを理解する
(※ 用語としての 「数直線」の学習は3年生です)
- 一つの数を、他の数の和や差として見る といった見方で、他の数と関係付けてみる
- 一つの数を、その数としてだけではなく、合成や分解により 構成的に見ることが出来るようにしていき、数の概念を形成していく
- 2位数は 「10のまとまりの個数 と 端数」 という数え方を基にして表されていることを理解する
- 「一の位」 「十の位」 の意味と用語を理解する
(例えば 「24」 ならば 「一の位は4、十の位は2」 であり、1が4個と10が2個 あることを意味している、ということを理解する) - 数を 「数の単位のいくつ分の集まり」 と捉えたり、図や物で表したりすることで、数の大きさについての感覚と共に用いられるようにする
- 実際の物や絵などでは多くなると扱いにくくなる数でも、この表し方だと簡単に数の大小が判断できたり、計算が簡単に行えるようになる、というこの表し方のメリットに徐々に気付けるようにする
- 120 程度までの3位数の表し方を知る
- 百より大きくなっても、下2桁は 1から 99 までを数えた時と同じように 変化していることに 気付く
(物を数えて、「100や10のまとまりの個数 と端数」 によって個数を表す活動などを通すようにする) - 3位数の表し方を知る過程で、2位数までの数の意味や表し方については確実に理解できるようにして、2年生での3位数の学習へと繋がるようにする
- 「10」 を単位として 数の大きさを 見ることが出来るようにする
(10のまとまりを作って数える活動 などを通す) - 「10」 を単位とした数の見方を学び理解していく過程で、数の構成についての理解を深めたり、「10」 を単位としてみていく加法・減法の計算の学習へと 繋がるようにしたりする
- いくつかずつにまとめて 数えてみる
(2ずつ・5ずつ・10ずつ など) - 1つずつ数えることと比べて、まとめて数えることの利便性に気付く
- 自分で、その場面に適した適当な大きさのまとまりを作って数え、整理して表す
- 10ずつ数えることを通して、数の表し方の理解の基礎を強化する
- 等分では、考え方の異なる2種類の分け方で 「同じ数ずつに分ける」ことを 練習する;
- ① ある数を「定められた数分に」同じ数ずつ分ける(「同じ数」が幾つなのかは不明)
→「何等分に分けるか」 が先に定められている(6個のアメを3袋に同じ数ずつ分ける、など) - ② ある数を「定められた同じ数ずつ」幾つか分に分ける(「幾つか分」が幾つなのかは不明)
→「何個ずつ分けるか」 が先に定められている(6個のアメを2個ずついくつかの袋に分ける、など)
- 例えば6個のアメについて、2袋や3袋に同じ数ずつ分けると何個ずつ分けられるか、や、2個ずつや3個ずつ 同じ数ずつ分けると 何袋に分けられるか、という分け方を行い、実際の操作や図で説明したり、分けられた結果を式に表したりする
- このような活動を通して、6という一つの数を、3+3 や 2+2+2 と、いろいろな見方で捉えることが出来るようにしていき、数についての感覚を豊かにする

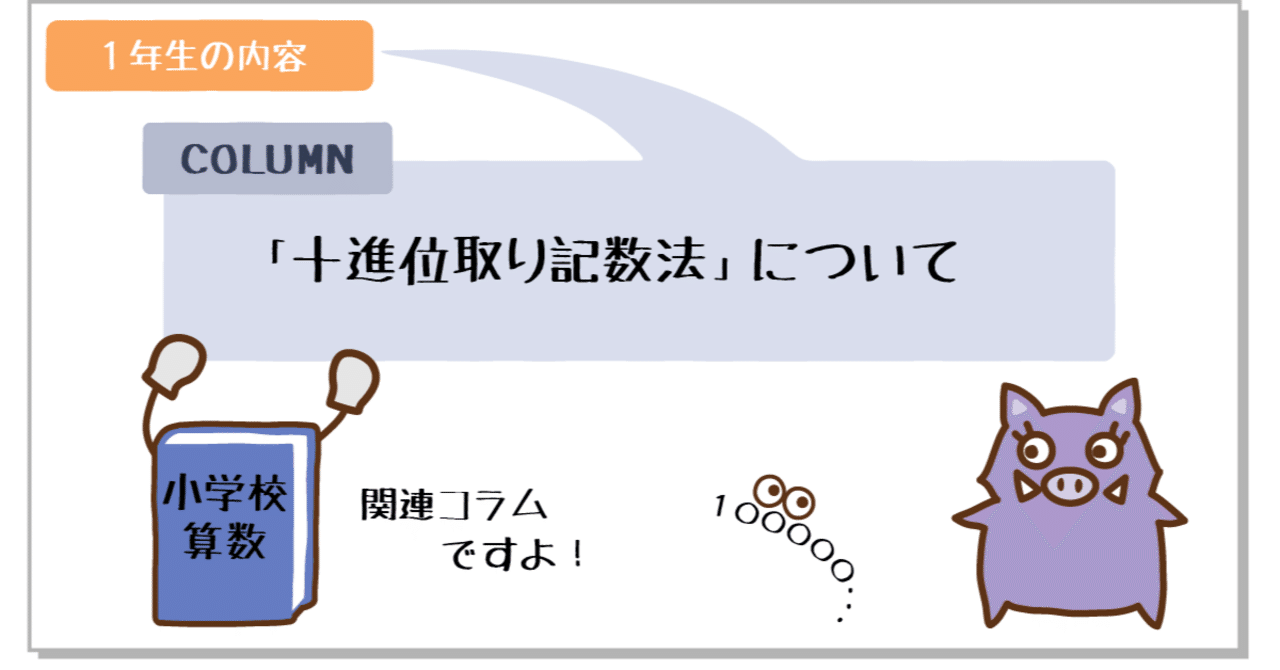
整数の加法・減法
- 加法は「二つの集合を合わせてできる集合の要素の個数」を求める演算であることを理解する
- 減法は「一つの集合を二つの集合に分けたときの、一方の集合の要素の個数」を求める演算であることを理解する
- 加法・減法が用いられる以下の場合を、理解して使えるようにする;
- 増加(例:リンゴが5個ありました、2個増えたら いくつになりますか)
- 合併(例:姉のリンゴは5個、弟のリンゴは2個あります、合わせるといくつになりますか)
- 順序数を含む加法
(例1:リンゴが5個あったので 縦一列に並べてみました、最後のリンゴは 前から5番目になりますが、その後ろにさらに2個 並べました、出来上がった列の 最後のリンゴは 前から何番目ですか)
(例2:赤いリンゴが5個、青リンゴが2個あったので 合わせて 縦一列に並べてみました、青リンゴは 前から2番目と、その4個後ろに並びました、後ろ側の青リンゴは 前から何番目ですか)
- 求残(例:リンゴが5個ありました、2個食べたら 残りはいくつになりますか)
- 求差(例:姉のリンゴは5個、弟のリンゴは2個あります、違いはいくつですか)
- 順序数を含む減法
(例1:リンゴが7個あったので 縦一列に並べてみました、最後のリンゴは 前から7番目になりますが、後ろの2個を 食べてしまいました、残った列の最後のリンゴは 前から何番目ですか)
(例2:赤いリンゴが5個、青リンゴが2個あったので 合わせて 縦一列に並べてみました、青リンゴは 後ろから2番目 (前から6番目) と、その4個前に並びました、手前側の青リンゴは 前から何番目ですか)
- 加法・減法が用いられる以下の場合を、なるべく理解して使えるようにする;
- 求大(例:弟のリンゴが2個あります、姉のリンゴは 弟のリンゴより3個多いです、姉のリンゴはいくつありますか)
- 異種のものの数量を含む加法
(例1:リンゴがいくつかありました、5人が1個ずつ持ち帰ったら2個残りました、リンゴは最初いくつありましたか)
(例2:リンゴが7個とみかんが2個あります、1人1個ずつ 果物を持ち帰りたいです、何人が持ち帰れますか)
- 求小(例:姉のリンゴが5個あります、弟のリンゴは 姉のリンゴより3個少ないです、弟のリンゴはいくつありますか)
- 異種のものの数量を含む減法
(例1:リンゴが7個ありました、5人が1個ずつ持ち帰りました、リンゴはいくつ残っていますか)
(例2:リンゴとみかんが合わせて9個ありました、9人が1個ずつ 果物を持ち帰ったら リンゴを持ち帰った人は7人でした、みかんを持ち帰った人は何人ですか)
- 加法や減法が用いられる具体的な場面を、 + や − の記号を用いた式に表す
- 具体的な場面について式を読み取る、逆に、式から場面を読み取って図や物を表す
- 式についての理解を深めて、式と具体的な場面とを結び付けられるようにする
- 1位数と1位数の加法と、その逆の減法の計算が確実に出来るようにする
(この範囲内での 繰り上がり・繰り下がりも含める) - このうち、和が10以上になる加法と その逆の減法(つまり繰り上がり・繰り下がり)は、「10と あといくつ」という数の見方を使って計算できるようにする
- 2位数になっても加法・減法の考え方や用いられ方は同じであることを理解する
- 次のような簡単な2位数の加法・減法を行いながら 数についての理解を一層深める;
- ① 十を単位としてみられる数の加法・減法
( 30+20 や 80−50のような、一の位が0の2位数同士の計算について、十を単位とした数の見方に関連させて、3+2や 8−5を基にして求めることが出来るようにする)
(※ただし1年生では和も2位数になるものに限り、和が3位数になるような計算の学習は2年生です) - ② 2位数と1位数との加法・減法で 繰り上がりや繰り下がりのないもの
- これらの計算を通して、「1位数までの計算」 と 「2位数までの数」 の理解を確実なものにする
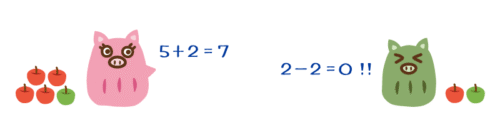
※ご注意事項
※ ご紹介する単元名や項目名は、学習内容の意味的なまとまりをご紹介するために、学習指導要領や子供達の教科書等を参考に、作成者が個人的にまとめたものです。学習指導要領や各教科書および参考書等での、実際の括り方や 用いられている名称とは 異なる場合もありますので ご了承ください。
※ 調査や要約等には 細心の注意を払い、出来る限り正確な内容となるよう努めていますが、あくまでも全て、個人の解釈です。内容を保障するものではありませんので、ご了承ください。
おわりに
以上で、1年生算数【数と計算】領域の、各項目の詳細説明は終了です。
各学年とも、学ぶ領域は4つずつありますので、項目説明は続きます♪
次回は、「小学校算数1年生の項目詳細【図形】」です。
それでは(^^)/